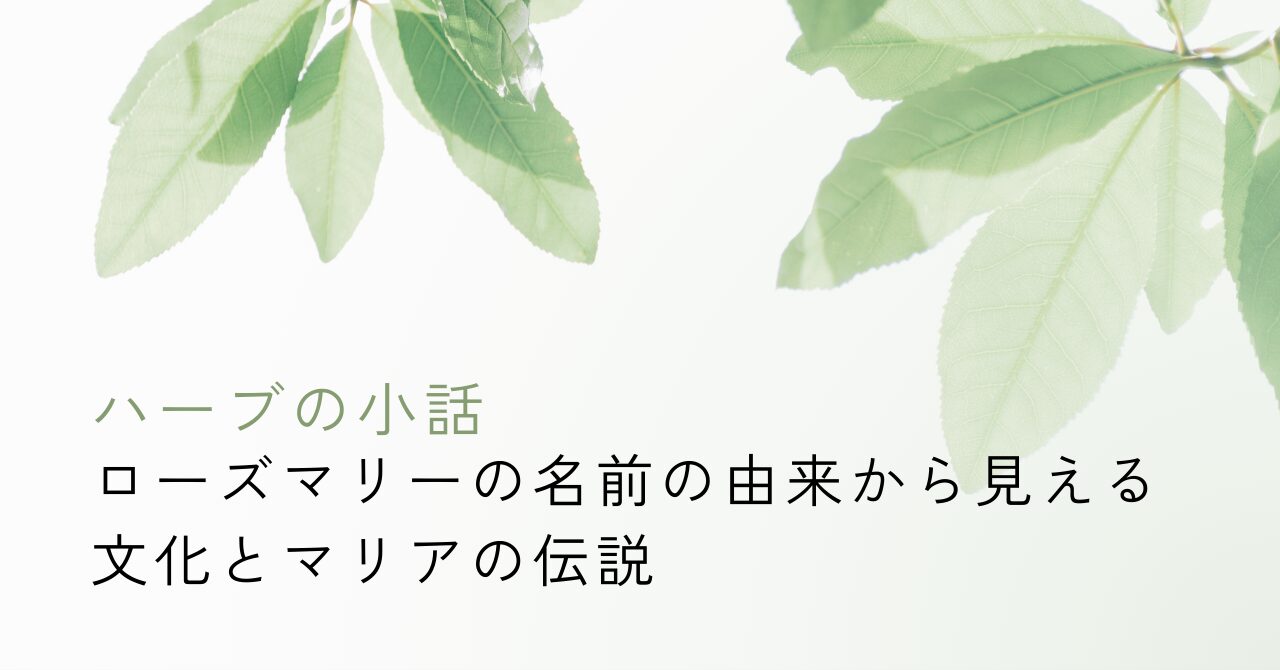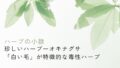ローズマリー、それは世界中でよく利用されているポピュラーなハーブ。
アロマテラピーから料理まで様々な用途で使われていますが、その名前の由来を考えたことはありますか?
ローズマリーの名前の由来を知ることで、ローズマリーへの見方が変わるかもしれません。
ローズマリーの由来は2つある

ローズマリーの名前には、「自生場所」に関する意味と「ある伝説」に基づく意味、2つの説があります。
どちらが真実かはいまだに解明されていませんが、どちらにしろ興味深いものなのでご紹介しましょう。
①自生場所が由来説
ローズマリーの学名は「Rosmarinus officinalis」と言い、ラテン語の「ros(露)」と「marinus(海の)」に由来します。
ローズマリーは地中海沿岸に自生しており、海からの霧で葉に露がつくことが多かったことからこの名が名付けられたと言われています。
②聖母マリアの伝説
もう一つの説は、「Virgin Mary’s Rose(聖母マリアのバラ)」が訛ったとされるものです。
訛ることで「Rose of Mary」となり、現在の「Rosemary」になったと言われています。
これは、聖母マリアが青いマントを広げた際に、白いローズマリーの花が青く色づいたという伝説に基づいています。
この逸話から、古来よりローズマリーが人々の身近な存在だったことがわかりますね。
ローズマリーから見える歴史と文化

ローズマリーには、紀元前より様々な用途がありました。
古代から中世の使用方法から、ローズマリーの効能とその神聖さが見えてきますよ。
古代より色んな地域で利用された
古代ギリシャは試験に
古代ギリシャでは、「学生たちが試験の際にローズマリーの冠をかぶっていた」という記録が残っています。
これは、記憶力を高める効果を期待してのことでした。
現在でも、ローズマリーの香りは集中力を高めるとされていますよ。
古代エジプトはミイラに
古代エジプトでは、「ミイラの防腐処理」にローズマリーが使用されていました。
その強い抗菌作用が、防腐効果をもたらしていたとされています。
これはローズマリーだけでなく、ラベンダーなどの精油も使用されていたようです。
中世ヨーロッパは2つの大きな利用方法が
結婚式に
ローズマリーは、中世ヨーロッパの結婚式において特別な意味を持つハーブでした。
花嫁は、純白のドレスにローズマリーの小枝を織り込んだ冠をかぶり、新鮮なローズマリーを束ねたブーケを手にしていたそうです。
また、結婚式の参列者たちには小さなローズマリーの枝が配られ、新郎新婦の寝室にもローズマリーが飾られました。
この習慣には、「記憶のハーブ」とされるローズマリーの特性が深く関わっています。
先ほど古代ギリシャでは、「記憶力向上のためにローズマリーを利用した」とご紹介しましたね。
そう、これは単なる装飾品ではなく「結婚の誓いを永遠に記憶にとどめる」という願いが込められていたのです。
永遠の愛を誓ったことを忘れないため、ローズマリーの効能にあやかった風習だったようですね。
ローズマリーのさわやかな香りに包まれた結婚式なんて、なんとも素敵です。
ペスト予防としての活用
中世ヨーロッパでは、華やかな結婚式とは程遠い活用方法もありました。
それは14世紀、「ペスト大流行時の予防薬」としての活用です。
ローズマリーの強い抗菌作用に期待され、こうように利用されていました。
- 室内での燻蒸
- 防護服への活用
- 消毒用の軟膏の原料
ペスト流行時には、ローズマリーをはじめラベンダーなどのハーブがたくさん活用された記録が残っています。
まとめ
ローズマリーの名前の由来には2つの説がありました。
1つは自生場所に関するもので、もう1つは聖母マリアの逸話に関するもの。
また、古代から中世まで様々な習慣や歴史的事件に関わっていたこともご紹介しました。
こういった背景を知ることで、ローズマリーの香りの楽しみ方が広がる気がしますよね。