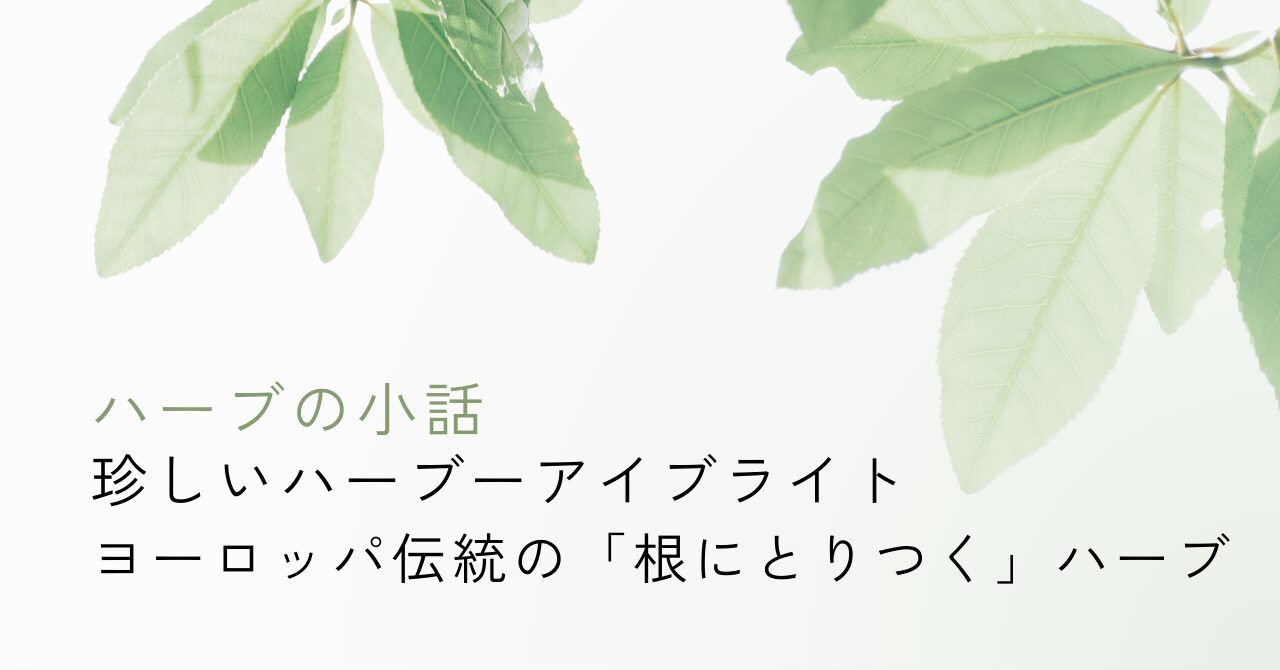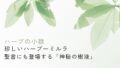「アイブライト」というハーブはご存知でしょうか?
日本ではなじみがありませんが、ヨーロッパでは古くから利用されてきた歴史あるハーブです。
この珍しいハーブを知ることで、中世ヨーロッパの知られざる生活が見えてきますよ。
アイブライトは香りを楽しむハーブではない

アイブライトは、ハーブですが香りはほとんどありません。
ではなぜ「ハーブ」とされているのでしょうか?
それは、「アイブライト」の効能にあります。
このハーブには、目の健康に寄与する様々な有効成分が含まれているそうなんです。
そのため、ヨーロッパでは昔からお茶などに利用され親しまれてきました。
アイブライトの名前の由来は効能そのまま

アイブライトという名前は、「Eye bright」の文字通り「目を明るくする」という意味に由来しています。
実はこの名の起源には、古代の薬学教義が関係しているんです。
ヨーロッパでは古くから、アイブライトの花の模様が人間の目に似ていることから「目を癒す力がある」と考えられていました。
これは「ドクトリン・オブ・シグネチャー」という考え方に基づいています。
「ドクトリン・オブ・シグネチャー」とは?
人間の体の一部分に似ている植物は、その対応する体の部分に薬効があるとする古代ギリシャから伝わる教義。
植物の形や特徴は、その効能を神が示したサインだとされていたんですね。
そのため花の模様が目に見えるアイブライトも、目に良いと信じられていたそうです。
アイブライトの学名は目を癒した女神が由来

アイブライトの学名は「Euphrasia officinalis」。
「Euphrasia」はエウプロシュネ、ギリシャ神話の三美神の一人のことでしょう。
エウプロシュネは、盲人の目を治したとされる女神。
古来より目の効能が謳われていたため、アイブライトにこの学名が付けられたようです。
アイブライトの様々な歴史の小話

こうして古来より親しまれていたアイブライトは、様々なエピソードが残っているのでご紹介しましょう。
中世の修道院での活用
11世紀の修道院では、アイブライトを含む目薬が作られていました。
特に、写本の筆写に従事する修道士たちの間で重宝されていたとされています。
彼らは細かい文字を書き写す作業で目を酷使していたため、この目薬は貴重な目を癒す手段だったんですね。
伝説のヒーリングハーブ
さらに、中世の民間伝承にはアイブライトにまつわる伝説が多数残されています。
- 妖精たちが目の病を癒すためにこの花を使用したという伝説
- 賢者の石を探す錬金術師たちが、洞察力を高めるためにこのハーブを用いたという記録
- 占い師たちが未来を見通す力を得るために使用したという言い伝え
様々な伝説にもなるほど、神秘的なハーブとされていたようですね。
16世紀にはさらに一般的に親しまれるように
16世紀になると、アイブライトはハーブティー、ワイン、エールとして日常的に飲用されました。
17世紀にはイギリスのハーブ療法士ニコラス・カルペパーが記憶力の向上にも利用していたとされています。
アイブライトは他の植物の根に寄生する

美しい姿とその効能で親しまれているアイブライトですが、その生育方法はちょっと怖いんです。
というのも、アイブライトは「他の植物の根に寄生」する植物。
寄生した植物の根から栄養や水分を吸収して成長するのです。
しかし安心してください、秋には寄生した元の植物を枯らすことなく枯れるそうですよ。
まとめ
アイブライトは、香りを楽しむハーブではなく、花をお茶などにして楽しむハーブです。
その名は、花の模様が目に似ていることから目に効能があると信じられたことが由来しています。
ヨーロッパでは中世から親しまれ、なじみの深いハーブで、様々な伝承や小話があります。
しかし、生育方法は他の植物の根から栄養を吸収すると言うちょっと怖いものでした。