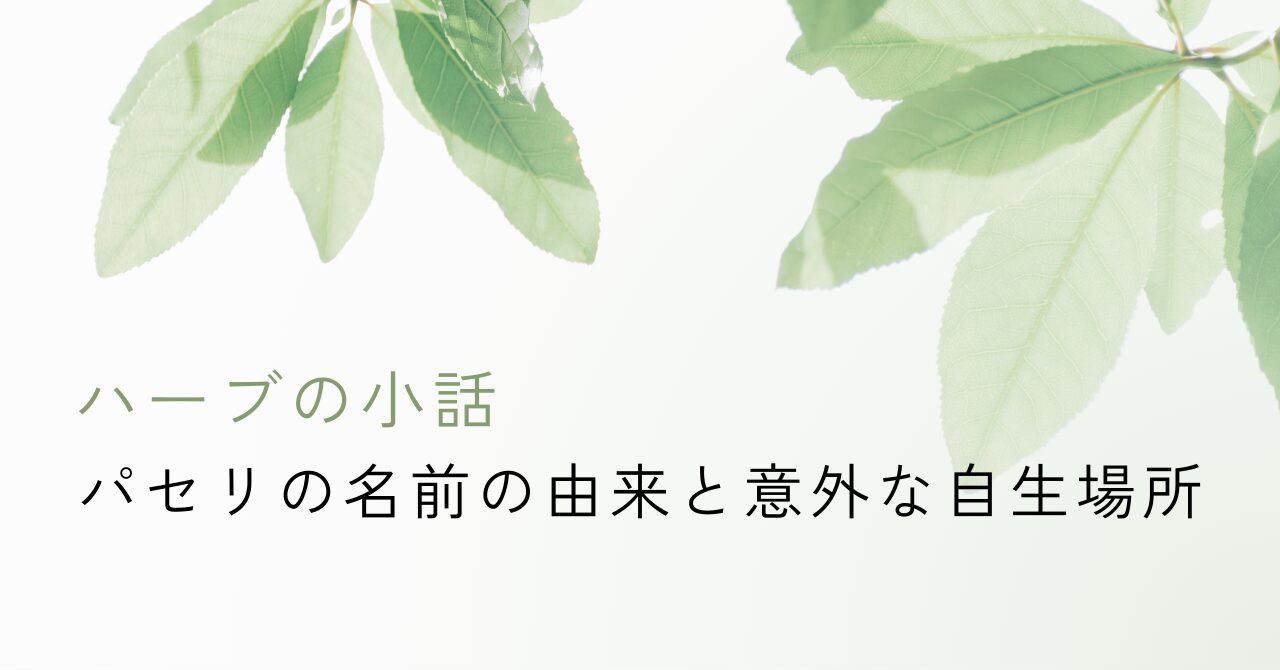パセリがなぜ「パセリ」と呼ばれるのか、気になったことはありませんか?
食卓にちょっとした彩りと味のアクセントを加える定番のハーブ、パセリ。
名前の由来を知ることで、何気なく口にしているパセリの印象が変わるかもしれませんよ。
パセリの名前の由来は、自生する場所

まず、パセリの学名からわかる意外な一面を見ていきましょう。
学名はギリシャ語由来
パセリの学名は「Petroselinum crispum」。
これは、ギリシャ語で「岩場に生える香草」という意味を持ちます。
「petros(岩)」と「selinon(セロリ)」というギリシャ語に由来するらしいのですが、なぜ岩なのでしょうか?
それは、パセリは古来より地中海沿岸の岩場に自生していたからなんですね。
パセリが岩場で育つ理由は?

岩場にパセリが自生しているなんて、なんか意外…そう思いませんでしたか?
実はパセリは長い年月をかけて、地中海の岩場の乾燥した土壌と、強い日差しに適応してきました。
特に特徴な進化が、発達した長い主根です。
主根とは、根っこの中心にある太い根のこと。
この主根が岩の隙間深くまで伸びることで、効率的に水分と栄養を吸収することができるのです。
岩場はパセリの生存戦略
そもそも、なぜ岩場を選んだの?
そんな難しそうな場所に適応するより、もっと育ちやすい場所があるんじゃない?
いいえ、パセリが岩場で自生することは、重要な生存戦略なんです!
- 他の植物が育ちにくい岩場では、生存競争が緩やか
- 日中に太陽光で温められた岩場は夜間もその熱を保持する
- 岩の隙間は強風からパセリを守り、種子が定着しやすい
岩場には、植物にとってこんなにメリットがあったんですね。
日本語の「パセリ」の由来は?

実は、正式な和名は「オランダゼリ」と言うんです。
江戸時代、パセリがオランダから輸入されたことでこの和名がつけられました。
ではなぜ「パセリ」と呼ぶのかと言うと、オランダ語での呼び名「peterselie」がそのまま定着したようですね。
まとめ
「岩場に生える香草」というギリシャ語だったパセリの学名。
一見育ちにくそうな岩場にパセリが自生していた理由は、パセリの生存戦略にありました。
日本では和名が「オランダゼリ」と言い、江戸時代にオランダから輸入されたことでこの名がついたようです。
「パセリ」の語源は、オランダ語での呼び名「peterselie」がそのまま定着したと言われています。